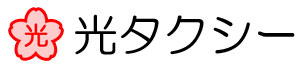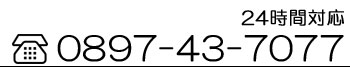どのような方がご利用できるのでしょうか?
65歳以上の方(第1号被保険者)及び40~65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)で、寝たきりや痴呆などで介護が必要となったり、家事や身の回り事など日常生活に支援が必要となった場合に介護保険のサービスを利用する事ができます。
◆第2号保険者の方は老化等に伴う15種類の特定疾病のいずれかが原因の場合のみ対象となります。
≪15種類の特定疾病≫
| 1.筋萎縮性側策硬化症 | 2.後縦靭帯骨化症 |
| 3.骨折を伴う骨粗しょう症 | 4.シャイ・ドレーガー症候群 |
| 5.初老期における痴呆 | 6.脊髄小脳変性症 |
| 7.脊柱管狭窄症 | 8.早老症 |
| 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 | 10.脳血管疾患 |
| 11.パーキンソン病 | 12.閉塞性動脈硬化症 |
| 13.慢性間接リウマチ | 14.慢性閉塞性肺疾患 |
| 15.両側の膝関節または股関節に著しい変形うお供なう変形性関節症 | |
申請からサービス利用までの流れ
1.まず申請
市役所の介護保険課の窓口に申請書に被保険者証と主治医の意見書を添付して申込みます。ご家族の方でも申請できます。 光介護支援センターでは、無料で申請手続きのお手伝いをさせて頂きます。

2.調査が行われます
市役所の担当者や委託された介護支援専門員などが申請者を訪問し、心身の状態や日常生活の動作など認定に必要な調査を行います。

3. 審 査
調査結果(コンピュターによる一次判定)と医師の意見書を元に、介護認定審査会(保険、医療、福祉の専門家で構成)で、どのくらいの介護が必要か要介護度の区分が行われ判定されます。

4. 認 定
保険者(市)は判定結果にもとずいて、要介護度を認定し申請から30日以内に申請者に通知されます。
介護サービス計画の作成
介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。
自分に必要なサービスをケアマネージャーに相談しケアプラン(介護サービス計画)を作ります。
作成費は無料です。
また、自分で作成することもできますと法律ではうたっておりますが、現実には難しいと思います。
サービスの利用
介護サービス計画に基づき、介護サービス事業者や介護保険施設と契約して、介護サービスが提供されます。
| 要介護状態認定区分 | 身体の状態(目安) |
| 要支援 1 | 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部動作に見守りや手助けが必要。 |
| 要支援 2 | 筋力が衰え、歩行・立ち上がりが不安定。介護が必要になる可能性が高い。 |
| 要介護 1 | 日常生活や立ち上がり、歩行に一部介助が必要。認知機能低下が少しみられる。 |
| 要介護 2 | 要介護1よりも日常生活動作にケアが必要で、認知機能の低下がみられる。 |
| 要介護 3 | 日常生活動作に全体な介助が必要で、立ち上がりや歩行には杖・歩行器・車いすを使用している状態。認知機能が低下し、見守りも必要になる。 |
| 要介護 4 | 要介護3以上に生活上のあらゆる場面で介助が必要。思考力や理解力も著しい低下がみられる。 |
| 要介護 5 | 日常生活全体で介助を必要とし、コミュニケーションを取るのも難しい状態。 |
| 介護サービスの自己負担額 |
||||
| 要介護状態認定区分 | 区分支給限度基準額(単位) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
| 要支援 1 | 5,032単位 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援 2 | 10,531単位 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護 1 | 16,765単位 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護 2 | 19,705単位 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護 3 | 27,048単位 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護 4 | 30,938単位 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護 5 | 36,217単位 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
| ※収入により1~3割負担になります。お電話、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。 |
||||
介護保険利用の大事なポイント
◆自由に選択
保険料を支払う利用者は、サービス提供者と契約関係になるため、介護サービスや事業所を自分で自由に選択して利用できます。
◆声をだそう
要介護者は高齢者が多い為、あまり希望や意見がでてきません。ケアマネージャーや保険者(市)に自分の本当に困っている事をどんどん相談しよう。その姿勢が介護保険法を良い方向に変えていきます。
◆介護保険制度は国民みんなで支えあう大事な保険です。
介護保険制度は、できて間もない為、不備や矛盾もたくさんあります。本当に困っていることでも保険では認めてくれない事もあります。これは使えない、これもだめとあきらめる前に、国や保険者に声を出す事が、より良い保険に変えていく唯一の手段です。無駄使いを避けながら、国民みんなで努力しましょう。
介護保険は「光介護支援センター」にお任せ下さい。TEL 0897-66-1199